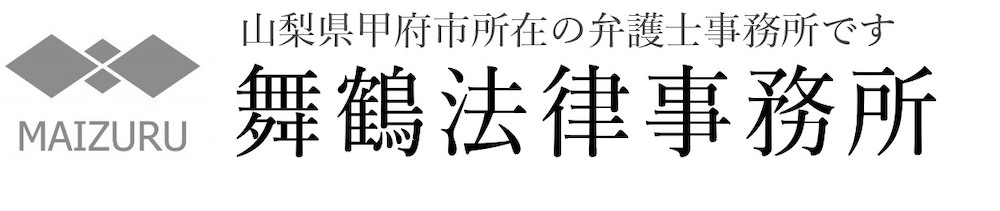目次
はじめに
問題の所在
権利者として請求する場合に、消滅時効という問題が発生することがあります。いろいろな事情で、権利発生からすぐに請求できないことがあります。この場合、一定期間の経過により、権利が時効により消滅してしまうことがあります。
時効が成立してその主張が認められると、請求権は消滅します。請求を起こすまでの数日の違いで、認められる権利が0か100かになりうるもので、実務上、非常に重要な指標となっています。
消滅時効の例
消滅時効の一例は、以下のとおりです。時効成立のおそれがある場合には、できるだけ保守的に早く請求しておくことが重要です。
なお、現行の民法や商法では、債権の種類により時効期間が異なるため、注意が必要です。
| 起算点 | 時効期間 | |
| 交通事故等の不法行為 | 損害及び加害者を知ってから | 3年(民法724条) |
| 貸金債権 | 弁済期から等 | 10年(民法167条) |
| 貸金債権(商事) | 同上 | 5年(商法522条) |
| 病院の治療費 | 同上 | 3年(民法170条) |
| 弁護士費用 | 同上 | 2年(民法172条) |
| 旅館等の宿泊費 | 同上 | 1年(174条) |
| 上記に関わらず、確定判決がある場合 | 判決確定時 | 10年(民法157条、174条の2 |
今回紹介する裁判例
消滅時効が成立することを妨げるために、時効の中断を図ることがあります。この方法の一つに、「裁判上の請求」という方法があります(民法147条1項)。時効期間満了前に裁判を起こしておくことで、裁判の判断が出るまで、時効が成立することはなくなります。また、裁判上の請求によらなくても、請求の意思を示して催告をしておくことで、時効成立から最大で6か月の時間を稼ぐこともできます(民法153条)。まずは催告をしておき、そこから6か月以内に訴訟提起などを行うことで、時効の中断とすることができます。
本件では、約4億円にも上る債権の一部である約5,000万円を明示して訴訟で請求し、後に残部の請求を、同じく訴訟にて行ったものです(判例タイムズ1390号、136ページ)。後の請求につき、消滅時効の成立が争われた事案で、結論としては時効の成立を認めています。
判決文について
以下のリンクにて、最高裁の本決定を掲載したページを閲覧できます(別ウィンドウが開きます)。関心がある方は、移動先のページから、判決文のpdfファイルをご覧ください。
事案の概要
| 紛争類型 | 遺言執行者が請求者、法人が債務者の事案 |
| 争点 | 商事の消滅時効(5年)の成否 |
| 時系列1 | H17.4.16、催告 |
| 時系列2 | H17.6.24が本来の時効期間 |
| 時系列3 | H17.10.14、約5,000万円を明示した請求 |
| 時系列4 | H21.4.24に全額認容(債権総額は約7,000万円と認定した) |
| 時系列5 | H21.6.30、残部(約2,000万円)の請求訴訟の提起 |
| 裁判所の判断 | 消滅時効は成立しているとして、遺言執行者の請求を棄却 |
| 裁判所の判断2 | 5,000万円の明示請求で時効中断するのは、5,000万円の部分のみ |
| 裁判所の判断3 | 時効成立後の裁判提起は、債権残部(約2,000万円)の催告に該当する(147条ではなく、153条の範疇) |
| 裁判所の判断4 | 時効期間後の再度の催告には、時効期間を先延ばしする効力はない |
判決要旨
債権の明示的一部請求と時効中断の範囲について
数量的に可分な債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合,当該訴えの提起による裁判上の請求としての消滅時効の中断の効力は,その一部についてのみ生ずるのであって,当該訴えの提起は,残部について,裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない(最高裁昭和31年(オ)第388号同34年2月20日第二小法廷判決・民集13巻2号209頁参照)。
そして,この理は,上記訴え(以下「明示的一部請求の訴え」という。)に係る訴訟において,弁済,相殺等により債権の一部が消滅している旨の抗弁が提出され,これに理由があると判断されたため,判決において上記債権の総額の認定がされたとしても,異なるものではないというべきである。
明示的一部請求の場合の、残部に及ぶ法的効果について
明示的一部請求の訴えが提起された場合,債権者が将来にわたって残部をおよそ請求しない旨の意思を明らかにしているなど,残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り,当該訴えの提起は,残部について,裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずるというべきであり,債権者は,当該訴えに係る訴訟の終了後6箇月以内に民法153条所定の措置を講ずることにより,残部について消滅時効を確定的に中断することができると解するのが相当である。
時効成立後の催告を裁判にて行った場合の法的効果について
消滅時効期間が経過した後,その経過前にした催告から6箇月以内に再び催告をしても,第1の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は,第1の催告から6箇月を経過することにより,消滅時効が完成するというべきである。この理は,第2の催告が明示的一部請求の訴えの提起による裁判上の催告であっても異なるものではない。
結論
「上告人は,本件催告から6箇月以内に,別件訴えを提起したにすぎず,本件残部について民法153条所定の措置を講じなかったのであるから,本件残部について消滅時効が完成していることは明らかである」
として、消滅時効の成立を認めた。
判決についてのコメント
明示的一部請求と時効中断の範囲について
貸金などの請求をするとしても、債務者から相殺が主張される可能性がある場合、最初からこの反論を折り込み、相殺後の債権額で請求を立てることがあります。裁判では、請求額の大小で収めるべき収入印紙代が異なるため、この節約といった意味合いもあると解されます。
明示的一部請求の場合は、民法147条にいう「時効の中断」は、明示した範囲にしか及ばないというのが、裁判所の一貫した姿勢です(最判S34.2.20)。このため、本件では、「相殺される範囲を検討するために、債権全体を審理の対象としているから、その裁判所の評価は受けない」という主張が展開されていたようです。とはいえ、「債権全体に対する判断は、判決理由中の判断に過ぎないから、あくまで時効中断は明示された範囲に限定される」という判断を受けています。
主張の範囲は原告が決めて提訴している以上、裁判所の評価もやむなし、といったところです。
催告の扱いについて
明示的一部請求は、債権残部の催告に該当するという最高裁の判断は、初めてのものでした。意思解釈としては不当でもなく、相殺の抗弁の判断などで債権全体が評価されるプロセスに照らしても、合理的に思われます。
ただし、催告自体には時効成立を6月延ばす効力しかありません(民法153条)。今回の判断は、その催告の方法が裁判による場合あっても、例外的な扱いはしないというものです。そして、時効成立後に催告をしても、特段の効力は発生しないため、時効成立はやむなし、という判断です。
結局、裁判所の判断を前提とする以上、理屈を詰めていくと、時効成立は避けがたいことになります。
本判決の意義等
時効成立が近い債権の場合、催告に頼るのではなく、時効成立までに裁判での請求などを行い、確定的な時効中断効を早期に得ておくべき、ということに尽きると考えます。
今回の判断は、教科書に掲載される類の一般論を展開しています。平成25年の判決時から現在に至るまでには、民法の教科書には加筆修正があったと思われます。私が受験していたころには出ていなかった判断であるものの、今の受験生は、当然のように知っている裁判例であると解されます。私としては、裁判例の存在自体は聞いたことがあったものの、今般改めて検討する機会があったため、本サイトでも紹介するものです。