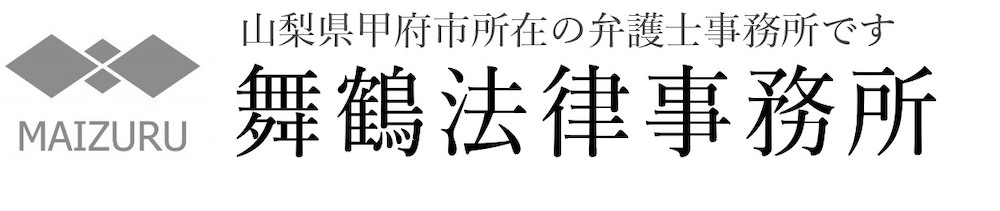目次
はじめに
交通事故で多い症状は、頸部や腰部の神経症状です。この症状につき、後遺障害に認定される場合、14級9号に該当することがあります。実際に症状が重いという場合には、より上位等級である12級13号に該当することもあるものの、件数としては、必ずしも多くないものです。
頚椎の後遺障害認定に関して問題になりうるのは、ヘルニアの既往症です。特に高齢の方に典型で、脊髄が経年変化することで、交通事故によるむちうち症と似たような症状が出ることになります。この経年変化と交通事故による受傷を区別することは、容易ではないものです。
今回紹介する裁判例は、交通事故による受傷で、12級の後遺障害相当であるとの主張にて被害者が請求していた事案です(自動車保険ジャーナル1987号・69頁より掲載)。結論としては、事故から4年前にヘルニアで手術していたことや、事故から約2か月後から神経症状の主訴が重くなっている点を捉えて、「交通事故と因果関係ある後遺障害ではない」という判断になっています。
なお、判決文中、「原告」との表記を、便宜上「被害者」としています。
事案の概要
| 事故日 | H24.10.1 |
| 事故態様 | 普通車同士の追突 |
| 主張する通院期間 | 通院約11月半 |
| 主張する症状 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫及び外傷性頚椎椎間板ヘルニア |
| 後遺障害等級(事前認定) | 非該当 |
| 特記事項1 | 交通事故4年前に腰椎椎間板ヘルニアの椎弓切除術を受けたことがある |
| 争点についての判断 | 交通事故と相当因果関係ある後遺障害は認められない |
判決要旨抜粋
交通事故と症状の相当因果関係を認定する際の判断枠組み
症状固定時の症状を外傷によると認めるためには、特段の事情がない限り、その症状が受傷後数日以内に発症し、症状固定の時期まで終始一貫して持続していることが必要である。外傷は外力が作用して生じる障害であり、外力が作用したときに組織が損傷し、その数日以内に組織損傷に由来する炎症反応等がピークとなるからである(ただし、骨折脱臼といった強い痛みをもたらす傷害の部位が併存しているときは、その痛みで他の部位の痛みがマスクされることはあり得る。)。
両手の症状についての判断
医療記録から、事故後約2か月後から主訴が強くなっている経緯を認定したうえで、
「外力によって組織破壊が起きた場合、受傷当日には「手指問題なし」と評価される状態であったのに、受傷から2ヶ月を経過した後に、症状が左手だけから両手に範囲が広がったり、手が動かなくなるほどしびれの症状が増強することは考えにくい(また、本件では骨折・脱臼した部位はない。)。したがって、症状固定時の両手のしびれ、物をよく落とす等の症状は、本件事故による症状であるとは認め難い(通院頻度や症状の発現経過に照らすと、【中略】頸椎及び腰椎の各椎間板ヘルニアが自然的経過により悪化した可能性が考えられる。)
とした。
両足の症状についての判断
医療記録から、事故後約2か月半後から主訴が強くなっている経緯を認定したうえで、
「被害者は、症状固定時の症状は、本件事故直後にはなく、数ヶ月してからはっきりしてきた旨述べている。外傷による場合、受傷後2,ヶ月以上経過した後に症状の範囲が左足のみから両足に広がったり、受傷直後に歩行安定と評されていた状態から、2ヶ月以上経過してから跛行に到ったり、歩行できないほど悪化することは考えにくい。したがって、【中略】、本件事故による症状であるとは認め難い。
とした。
椎間板の変形・膨隆と経年変化の関係についての判断
被害者の頸椎椎間板及び腰椎の椎問板の変性・膨隆はC3からC7にかけて、L3からSにかけてといった多発性の変性・膨隆であるところ【証拠関係略】、外力によって頸椎椎間板及び腰椎椎間板それぞれに多発性の変形・膨隆が生じる可能性は低い。また、被害者の椎間板の膨隆はいずれも加齢性の変性である骨棘を伴うものであった【証拠関係略】。さらに原告は、本件事故の約4年前である平成20年に腰椎椎間板ヘルニアの症状が生じ、その治療のためL4及びL5の椎弓切除術を受けた【証拠関係略】。
これらのことからすれば、被害者の椎間板の変形・膨隆は加齢性の変形・膨隆である可能性が相当にあり、本件事故の衝撃(外力)により形成されたと認めることはできない。
判決についてのコメント
後遺障害認定について
まず、裁判の前の後遺障害認定手続(事前認定)において、「非該当」となっていることが重要です。事前の医学的評価で後遺障害が残存していないとされている場合、これを裁判で覆すことは、困難が想定されるところです。
裁判では、事故後から症状が強くなる経過を細かく認定しています。そして、事故から2か月後から強まっている症状の状況や、事故以前のヘルニアの状況を評価したうえで、「交通事故と症状の相当因果関係があるとはいえない」とされています。
事故から期間が空いてからの症状となると、判決に示される判断枠組みのとおり、被害者に有利な認定を受けることは、やはり困難なことが多いというべきです。
本判決の意義
裁判では、事故と症状の相当因果関係が争われると、医療記録が重視される傾向にあるといえます。この医療記録で、事故後から一貫した症状の記載がないとなると、因果関係の認定では困難が予想されます。実際に症状があるという場合には、その旨をしっかりと医師に伝え、診断書に残してもらうことが重要と考えます。「医師の面談だと上手く症状を伝えることができない」という方もいますが、見えない痛みについて医師が適切に判断するためには、被害者の対応もどうしても重要になります。
判決では、概略、「骨折などで強い痛みがある場合は、他の部位の症状がマスクされることもありうる」と述べられています。事故内容によっては、痛みを強く感じる場所が変わっていくことがありうる、ということです。やはり、異状がある場合にはできるだけ通院し、その変化の状況も含めて、症状を医師に伝えることが重要というべきです。
認定内容一覧表
| 請求額(円) | 認定額(円) | |
| 治療費 | 408,268 | 408,268 |
| 文書料 | 43,980 | 43,980 |
| 通院交通費 | 15,300 | 15,300 |
| 休業損害 | 410,000 | 410,000 |
| 通院慰謝料 | 1,640,000 | 520,000 |
| 後遺障害慰謝料 | 3,500,000 | 0 |
| 後遺障害逸失利益 | 3,271,207 | 0 |
| 弁護士費用 | 890,000 | 100,000 |
| 既払い金 | ▲398,269 | ▲398,269 |
| 合計 | 9,780,487 | 1,099,280 |
補足
以下のページも、よろしければご覧ください。