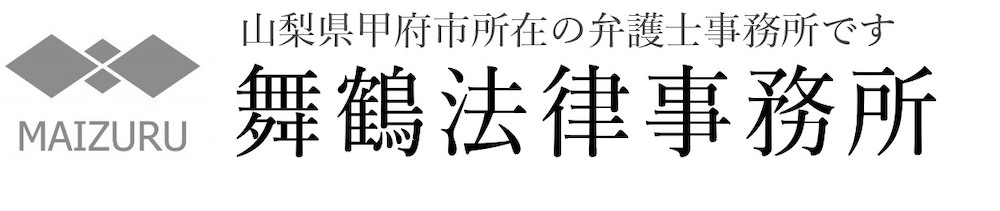別居中の夫婦は、収入のある側がない方に対して、「婚姻費用」の支払義務を負います。この支払い額について、家計に住宅ローンがある場合、争いが生じることがあります。ただし、この住宅ローンの金額につき、「控除する・しない」という扱いの明確なルールや算定方法はありません。
このため、住宅ローンを払っている側が婚姻費用を払う場合、ローン支払相当額がそのまま減額されるかというと、そう単純ではありません。事案により、さまざまな計算をしたり、現実的な支払い可能額と照らして調整していくということが求められます。
それでも、当事務所の過去の経験や判例に基づいて、一般的な事例を示すことはできます。ここでは、住宅ローンが婚姻費用に及ぼす影響について、解説します。
そもそも婚姻費用とは?
まず、「婚姻費用」は、生活費の支払いとしての意味を持ちます。別居中の夫婦であっても、互いの生活水準が同等になるよう助け合う義務があるとされます。そして、「婚姻費用」とはこの義務を果たすために支払われる金額ということになります。
婚姻費用の法的根拠は、民法760条となります。同条には、「(婚姻費用の分担)夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とあります

住宅ローンと別居中の婚姻費用の関係
上記のとおり、住宅ローンがある場合の婚姻費用の計算につき、明確なルールや算定方法は、ありません。よって、具体的な支払額については、双方が合意して決めていくべきということになります。
ただし、合意した婚姻費用額は、その後の離婚協議において、一定の影響を与えるものです。例えば、養育費や、慰謝料の金額算定といった局面での影響が考えられます(この点については後述します)。よって、婚姻費用の算定には、家庭の実情を踏まえたうえで、妥当な金額で合意しておくべきといえます。
一般的に考えれば、住宅ローンの借り入れの名義は、夫婦のうちの夫であることが多いところです。また、統計的には、夫の収入の方が妻より多いといえます。よって、住宅ローンの支払者と婚姻費用の支払者(法律的には「義務者」と呼ぶ)は、同じ(多くの場合は夫)であることが多いといえます。
以下では、統計的に最も多いと解される、「夫が住宅ローンを払っていて、婚姻費用の支払義務者でもある」という事案に限定して、住宅ローンが婚姻費用に与える影響をみていきます。
住宅ローンを払っている義務者がその住宅に居住するケース
婚姻費用を受けとる側(権利者)は、その住宅には住んでいない状態です。よって、権利者は、「不動産に居住する」という利益を享受することはありません。よって、婚姻費用の額は、支払う側の収入から住宅ローンを控除せずに計算されることが多いといえます。
住宅ローンを払っている義務者が、その住宅に居住しないケース
権利者は、不動産に居住するという利益を得ています。よって、婚姻費用の計算にあたっては、支払う側の収入から住宅ローンから相当額を控除して計算されることが多いといえます。
ただし、住宅ローンの実際の支払額全額が控除されるかというと、それは事案によります。ローン期間が短い場合には毎月の支払額も大きくなり、「住宅ローンを考慮するとそれ以外に権利者に生活費として支払うものはない」という状況になることも理論上はありうるところ、そのような扱いは妥当でないことも多いためです。
具体的なケース〜夫婦の収入の影響を加味して
婚姻費用を算定する際には、夫婦双方の収入を参照します。ここでは、具体的な年収例で、婚姻費用の算定額例を示します。
これは、養育費・婚姻費用算定表(令和元年12月23日 最高裁判所公表)に基づくものです。ただし、あくまで例ですので、実際の婚姻費用は変わりうることをご了承ください。
ケース1:夫の年収500万、妻の年収100万、小学生の子どもが一人
| 婚姻期間 | 10年程度 |
| 別居時期 | 3年程度 |
| 夫の年収 | 500万円(会社員) |
| 妻の年収 | 100万円 |
| 住宅ローン残高(月の返済額) | 1500万(6万円) |
| 当該住宅の居住者 | 妻 |
| 子について | 小学生の子ども1人(妻と同居) |
| 婚姻費用請求の方向 | 妻→夫 |
| その他 | 不貞などの明確な離婚理由なし |
| ↓ | ↓ |
| 想定されうる婚姻費用 | 月額2〜8万円 |
| (住宅ローンがない場合の婚姻費用) | 月額8〜10万円 |
ケース2:夫の年収600万、妻の年収200万、15歳上の子どもが2人
| 婚姻期間 | 10年程度 |
| 別居時期 | 3年程度 |
| 夫の年収 | 600万円(会社員) |
| 妻の年収 | 200万円 |
| 住宅ローン残高(月の返済額) | 1000万(4万円) |
| 当該住宅の居住者 | 妻 |
| 子について | 15歳以上の子ども2人(妻と同居) |
| 婚姻費用請求の方向 | 妻→夫 |
| その他 | 不貞などの明確な離婚理由なし |
| ↓ | ↓ |
| 想定されうる婚姻費用 | 月額8〜12万円 |
| (住宅ローンがない場合の婚姻費用) | 月額12〜14万円 |
以上のとおり、「住宅ローンの支払いがあり、権利者がその住宅に居住している」というような場合には、その事情が婚姻費用の算定に影響を与えていることが分かります。子どもの人数や年齢と同様に、金額算定における考慮要素になるというべきものです。

婚姻費用の額は「養育費」や「慰謝料」に影響する
当事者間で婚姻費用の金額に関する合意内容や交渉経緯が、離婚協議における養育費や慰謝料の額に間接的に影響を与えることがあります。
養育費への影響
「養育費」とは、子どもの衣食住や教育、医療費、娯楽費(小遣いなど)にかかる費用を指します。婚姻費用には配偶者の生活費も含まれますが、養育費は子どものための支払いであるというイメージです。
このように、婚姻費用と養育費は、性質が近いものです。よって、婚姻費用で合意した金額は、養育費の金額を決めるうえでも参照されることが多いといえます。
慰謝料への影響
婚姻費用の金額が、慰謝料の算定に直接影響を与えるわけではありません。とはいえ、婚姻費用を決めるうえでは、所得資料を確認するなどして、経済状況や支払能力の確認をします。この資料の状況によっては、「収入があるにもかかわらず、配偶者に充分な生活費を渡していない」として、「経済的DVだ」とする根拠になることもあります。その反対のケースもあります。
このように、婚姻費用をめぐるやり取りの内容が、その後の離婚に関する交渉に影響を与えることがあります。
婚姻費用を弁護士に相談するメリットは?
婚姻費用の算定や相手方との交渉にあたり、弁護士に相談したり依頼するメリットについては、以下の点が挙げられます。
適正な婚姻費用を算定できる
婚姻費用は、夫婦の収入や生活状況に応じて決まります。弁護士に依頼すれば、前述の裁判所の婚姻費用算定表や個別の事情を考慮して、適正な金額を算出していくことができるといえます。婚姻費用の算定は、いわゆる「算定表」による一般的な計算にあてはまらない事案の場合には、なかなか見通しを立てることが難しいものです。その算定の助けになるといえます。
相手との合意を公正に進められる
婚姻費用の請求をしても、「相手方が低い金額しか提示してこない」、「そもそも交渉の席につかない」、「連絡すら取れない」というような場合もあります。弁護士が代理人として交渉することで、適正な金額での合意が得やすくなります。
また、後述のとおり、調停などの法的手続を取るタイミングについても、妥当な判断がしやすくなるといえます。
精神的な負担を軽減できる
夫婦間の金銭面での交渉は、精神的な負担が大きいものといえます。特に子育て世代の場合には、日々の生活に加えて夫婦間のやり取りもしなければならないということになります。この負担は大変なものです。
弁護士に任せることで、本人が相手方に直接会うことを避けられます。交渉の窓口を適切に用意することで、感情的対立を避けながら交渉を進めるという対応が実現できます。
調停や裁判になった場合にスムーズに対応できる
婚姻費用は、日々の生活費です。そのような性質上、双方の話し合いで早期に合意できれば、最も望ましいところです。ただし、お金の話ですので、容易に折り合えない問うケースも、多くあります。
そのような場合には、「内容証明を送付して支払いを請求する」といったことや、「家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申し立てを行う」ということも必要になるケースが、それなりに多くあります。
この判断や対応につき、弁護士が代理人として関与していれば、スムーズに進めることができるといえます。
以上、「住宅ローンを払っていると婚姻費用は減額される⁉」でした。
婚姻費用は、決して小さい額ではありません。また、支払いが長期にわたり続くこともあります。このため、支払義務者が支払いを拒否したり、妥当な婚姻費用について合意が得られないといった事態も、しばしば起こります。
そのような場合には、弁護士に婚姻費用の交渉や支払請求について依頼をご検討ください。