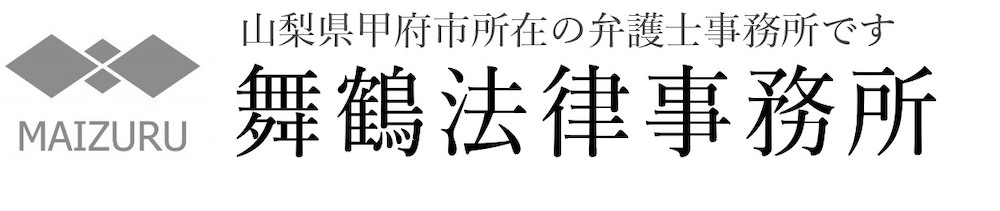成年後見人の弁護士が被後見人の財産を使い込んだ事案で、刑事手続となっていたものがありました。この事案につき、東京地方裁判所は、2013年10月30日付の判決で、懲役5年の実刑判決を出しました。
着不金額は約4,200万円ということで、被害金額や、弁護士という専門職が後見人に就任していたにも関わらず横領に及んだという事案の社会的影響を考慮して、実刑判決としたのでしょう。
残念ながら、弁護士によるこの種の事案は後を絶ちません。昔から横領事案はあったようですが、成年後見制度の本格化を受けて、成年後見事件も増加する中、このような横領事案も増加傾向にあるように感じます。
成年後見人と弁護士
一般論として、お金があるところに、常に着服があります。
他方、弁護士であれば、法律知識は一定水準以上のものが担保されているものと考えられます。そうであれば、弁護士は、専門職後見人として、適切な有資格者であると思います。
かつてのように多くの弁護士が経済的に豊かであれば、このような犯罪も相対的に少なかったかもしれません。しかし、今後弁護士が増員され、それに呼応するようにこの種の犯罪が増加するようになると、裁判所から弁護士を成年後見人として選任することを嫌がられるおそれがあります。
そのような展開は、弁護士業界にとって業務を失う損失であると同時に、社会的にも大きな損失であると思われます。
となると、弁護士の業務として成年後見制度に関与していくためには、裁判所の監督強化や判決の重罰化が進行するのは、避けられない流れかもしれません。弁護士自治にも掉さすような流れともいえ、率直に、嫌な傾向であると考えます。
後⾒⼈・成年後⾒⼈とは?
以下では、後見制度について、その概略を説明します。
「後見人(こうけんにん)」とは、広義には、①未成年者を対象とする「未成年後見人」と②成人を対象とする「成年後見人」を指します。ただし、一般的には、②の「成年後見人」の方を指す場合が多いといえます。
成年後⾒⼈は、判断能力が欠けてしまっている成人の方の代わりとなって、その人の財産管理や生活に関する事務を行います。成年後見人にはそのような権限が法的に認められていて、「法定代理人」と位置付けられます。具体的には、知的障害のある方、精神障害のある方、認知症の高齢者などにつき、本人の財産管理や身上監護を行います。
成年後見人は、申立権者からの申し立てを受けて、家庭裁判所によって選任されます。
成年後⾒制度とは?
「成年後見制度」とは、判断能力が不十分な状態の方の権利や財産が守るための制度です。このような方々が不利益を被らず、生活が支援されるように定められています。本人の意思を尊重しながら、本人の生活状況や心身の状態を鑑みて代理を行います。
今後、成年後見制度はますます社会的に重要になるものといわれています。高齢化がますます進むことで、必然的に認知症の方も増えるであろうことが、その大きな要因です。
成年後見制度には、予め備える「任意後見」、すでに判断能力が低下した方の「法定後見」があります。また、本人の判断能力の程度によって、「後見人」「保佐人」「補助人」の3つの区分があります。
| 区分 | 対象となる方 | 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為 | 成年後見人等が代理することができる行為 |
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 (例:重度の認知症) | 原則としてすべての法律行為 | 原則としてすべての法律行為 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 (例:中程度の認知症) | 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為。 | 申立てにより裁判所が定める行為 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 (例:軽度の認知症) | 申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める行為。特定の法律行為のみ、本人の同意を得て、代理権や同意権を与えられる。 |
具体的な手続きや法律行為は「成年後見制度について(裁判所)」に記載されていますが、以下に要約します。
財産管理・出金・支払い
本人の預貯金の管理、不動産の売買契約・賃貸契約、有価証券の保管、年金などの収入管理を行い、税金や医療費などのほか、以下のような各種費用の支払いも行います。
- 福祉サービスの利用費用
- 生活費、入院費
- 各種税金
- 負債の返済
- 本人名義で出す香典、祝儀、法事費用など
- 本人のため弁護士費用
身上監護
本人が受ける介護サービスや施設の入退所の契約、治療や入院の手続・契約、住居の確保など、身上監護のための仕事や手続きを行います。生活全般にわたって本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら後見人としての役目を果たしていくことが求められます。
ただし、後見人自身が食事の世話や介護などを行うことは、通常はありません。また、微妙な問題ですが、後見人には本人の医療行為への同意・不同意の決定権はないというべきです。また、婚姻、離婚、養子縁組、遺言などは、後見人が代理することはできません。
出納記録の管理
本人の生活費や受け取った年金など収支記録は出納帳に記録するなどして、適切に管理します。裁判所かに対して行う定期的な報告の際に、必要に応じてこれらの資料を提出します。

後見人に報酬は支払われるの?報酬額は?
後見人は、本人(被後見人)の財産から報酬を受け取ることができます。ただし、勝手に本人の財産から受け取ることはできません。このような費用支払いを勝手に進めてしまうと、悪質と判断されれば、冒頭で記載したような横領事案となってしまうおそれがあります。
実際には、後見人から家庭裁判所に「報酬付与」の申し立てを行い、家庭裁判所が後見人の報酬額を決定します。裁判所の決定は、「審判」という方式によりなされます。
原則として、報酬は本人(被後見人)の財産から受け取ることになっています。とはいえ、本人の財産からの支払いが困難な場合は、自治体による金銭支援制度を利用できることもあります。