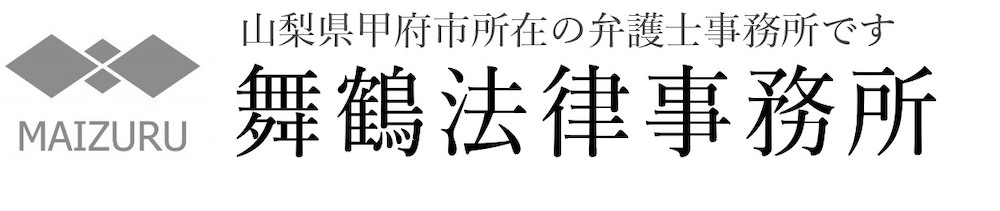目次
はじめに
相続事件では、「遺留分」が問題になることがあります。遺留分とは、遺言などによっても奪えない法定相続人の最低限の権利とされています。相続人の状況によって変動するものの、「法定相続分の3分の1から2分の1」といった割合で認められています。このため、被相続人(亡くなった人)が「全財産を相続人の一人のみに相続させる」と遺言していても、遺留分をめぐる相続問題は完結しないことになります。
遺留分は、非常に強力な権利である反面、権利行使までの時効期間が1年であるなど、制約も多いものです。
この遺留分の意思表示(遺留分減殺請求権の行使)の有無及びその時期について、具体的な事情に即して判断した事例につき、紹介します(判例タイムズ1431号218ページ)。
なお、当事者の記載を、便宜上、判決文などからは変更しています。
前提・遺留分割合
遺留分割合は、以下のとおり定められています(民法1028条)。ざっくり書けば、被相続人からみて配偶者や父母や子の場合、3分の1から2分の1の割合で認められている権利、といったところです(兄弟には遺留分はない)。
- 被相続人の父母(及び配偶者)が相続人:相続財産の3分の1
- 上記以外の場合(配偶者と子、子のみが相続人といった場合):相続財産の2分の1
- ただし、兄弟には遺留分はない
前提・遺留分減殺請求権の消滅時効(民法1042条)
遺留分の消滅時効は、要するに、「贈与の状況を知るなど、遺留分権行使が可能になった時点から1年」ということになります。一方、相続から10年経過した場合には、無条件で権利消滅ということになります。
- 遺留分権利者が相続の開始及び現在すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年の経過(時効期間)
- 相続開始の時から10年の経過(除斥期間)
事案の概要
| 争点 | 遺留分減殺請求の意思表示の有無及びその時期 |
| 前提1 | 被相続人は、H21.4.3死亡 |
| 前提2 | 遺産分割協議の始期はH21.10.4 |
| 前提3 | 本件に先行して、相続問題に関して2件の訴訟あり(本件請求者敗訴) |
| 請求側の主張1 | 遺産の状況がわからなかったため、遺留分権行使が可能な時期はH25.7.24であった |
| 請求側の主張2 | 遺留分権行使は、H26.7.18に行った |
| 請求側の主張3 | 主張2が通らなくとも、先行する訴訟での主張などに、遺留分減殺請求権行使の意思表示が存在する |
| 裁判所の判断1 | 遅くともH25.2.14(先行した訴訟判決日)ころには遺留分減殺請求権行使可能(時効の起算点) |
| 裁判所の判断2 | 先行訴訟の請求者の主張に、遺留分減殺請求権行使の意思表示は含まれない |
| 裁判所の判断3 | 請求者は、H25.2.14ころから1年経過後のH26.7.18に遺留分減殺請求権の行使をしているため、消滅時効成立(請求者敗訴) |
判決要旨抜粋
遺留分減殺請求権の消滅時効の起算点を確定する際に考慮すべき原則について
民法1042条にいう減殺すべき贈与があったことを知った時とは,贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時と解すべきである。そして遺留分権利者が贈与の無効を信じて訴訟上抗争しているような場合は,贈与の事実を知っただけで直ちに減殺できる贈与があったことまでを知っていたものと断定することはできないが,民法が遺留分減殺請求権につき特別の短期消滅時効を規定した趣旨に鑑みれば,遺留分権利者が訴訟上無効の主張をしさえすれば,それが根拠のない言いがかりにすぎない場合であっても時効は進行を始めないとするのは,相当でないと解すべきである(以上につき,昭和57年判決参照)。
本件での消滅時効の起算点について
先行する訴訟の事実関係を認定したうえで、
「請求者らが第一次訴訟の控訴審判決の主文及び判決理由を知った平成25年2月14日(同判決の言渡日)又はこれに近い時期においては,請求者らは,贈与の無効ないし不存在に係る主張が根拠を欠くことを認識し,または,認識し得べき状態にあったというべきであり,遅くとも同時期には,請求者らが贈与の存在及びこれが減殺できるものであることを知っていたことが推認される」
とした。
遺留分減殺請求権の行使の有無について
遺産協議での請求者の対応や、先行した訴訟の準備書面などの記載に、明示又は黙示の遺留分減殺請求権の行使の意思表示が含まれるという判断は、しなかった。その他にも、先行する訴訟の証拠関係等を子細に検討したうえで、それらの手続中などの時期(明確に権利主張したH26.7.18以前)に、遺留分減殺請求権を行使した又は行使したと同視されるような状況はない、とした。
判決についてのコメント
遺留分減殺請求権の行使状況について
先行した訴訟の証拠など細かく認定して、遺留分減殺請求権の消滅時効の起算点と、時効期間内に権利行使があったといえるかどうかの判断を行っています。認定は相当に細かいため、すべてここで紹介できる性質のものでもありません。ある程度抽象化すると、①明確に権利行使の意思がなされていないため、先行する訴訟の準備書面などの主張で、遺留分減殺請求権の行使があったとは解されない、②遺産分割協議に応じなかったことで黙示の遺留分減殺請求権の意思表示があったとはいえない、という評価になると考えます。
過去の裁判例との比較
「遺留分減殺請求権」自体がマイナーである事情もあってか、時効期間が1年と短い同権利の行使などをめぐっては、過去にも様々な紛争があります。本件に関わるものでその内容を簡単にまとめると、概ね以下のとおりです。
最高裁S57.11.12第二小法廷判決(民集36巻11号2193頁)
遺留分減殺請求権の消滅時効の起算点について、「民法1042条にいう「減殺すべき贈与があったことを知った時」とは、贈与の事実およびこれが減殺できるものであることを知った時と解すべき」とした。
上記認識の認定に関する原則論として、「民法が遺留分減殺請求権につき特別の短期消滅時効を規定した趣旨に鑑みれば、遺留分権利者が訴訟上無効の主張をしさえすれば、それが根拠のない言いがかりにすぎない場合であつても時効は進行を始めないとするのは相当でないから、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について、一応、事実上及び法律上の根拠があつて、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことがもつともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知つていたものと推認するのが相当というべきである」とした(本件でも参照された原則論です)。
京都地裁S60.4.30判決(金判721号32頁)
被相続人が、特定の相続人に所有不動産全部を相続させる遺言がある場合があった事案で、請求者が自分の分け前を要求して遺産分割協議書への押印を拒否した態度をもって、遺留分の権利を行使する意思の表示であるとした。
東京高裁H12.7.13判決(判タ1053号224頁)
遺留分権利者が遺言の無効を信じていたために遺留分減殺請求権を行使しなかったと主張した事案で、その対応がもっともといえる特段の事情の有無の認定として、裁判所は、その無効を信じた根拠が弱いと指摘し、遅くとも先行した訴訟の遺言の無効確認の訴えが棄却された第一審判決の送達を受けた日の翌日からは、遺留分減殺請求権の消滅時効が進行するとした。
東京高等裁判所平成4年7月20日判決(判時1432号73頁)
遺産分割協議の申し入れや調停の申し立てに遺留分減殺請求権行使の意思表示が含まれているかどうかが問題となった事案で、手続や法的効果の差異から、協議申し入れや調停提起につき、当然に遺留分減殺請求権行使の意思表示が含まれるものではないとした。
具体的な判断としても、遺留分減殺請求権の行使を認めなかった。
まとめ
- 遺留分減殺請求の意思がある場合には、早期に行うべき
- 意思表示は書面に残し、後に日付の特定などで疑義がないようにすべき
補足
以下のページも、よろしければご覧ください。